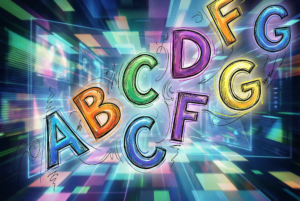日本では契約書や領収書に収入印紙を貼って税金を納める「印紙税」という制度があります。郵便局の窓口や一部のコンビニでは「郵便・切手類・印紙」と書かれた看板を目にしたことがあるでしょう。これは郵便切手だけでなく印紙税のための収入印紙も扱っている印(しるし)です。印紙税は、土地の売買契約書や工事の請負契約書、領収証など経済取引に伴い作成される文書に広く課税されるのが特徴です。契約書を作る背景にはお金のやりとり=経済的利益があるはずだという発想から、その文書を作ったことに対し比較的軽い負担(印紙税)を求める仕組みになっています。いわば「文書に貼る通行料」のようなもので、大事な契約書や領収書を作ったときに国庫へ収める税金です。
印紙税額一覧表(2025年現在)は下記のとおりです。印紙税法では課税対象となる文書を20種類(第1号文書~第20号文書)に分類しており、それぞれの文書ごとに印紙税額が定められています。課税文書の種類に応じて、収入印紙を1通(または1冊)あたり所定の金額貼り付けて納税します。文書の種類によって、金額が一定の**「定額税率」のものと、記載された契約金額や受取金額に応じて段階的に税額が上がる「階級定額税率」**(いわゆる累進課税のようなもの)のものがあります。例えば領収書や高額な契約書では金額に応じた段階課税、定款や預金通帳などでは一律の定額課税になっています。それでは、日本の印紙税額一覧を文書の種類ごとに見ていきましょう。
印紙税額一覧表(課税文書別・2025年現在)
各課税文書について、2025年現在の最新の印紙税額を一覧表にまとめました。契約書や領収書などの文書を作成する際には、この印紙税額一覧表を参考にして、該当する収入印紙を貼り付けます。印紙税額は長らく最小200円からとなっており、取引額が大きい文書ほど高額の印紙が必要です(例えば何十億円もの大型契約書には最大で60万円の印紙税)。なお、表中の「非課税」は印紙税がかからない文書を意味します。また「契約金額の記載のないもの」とは金額が書かれていない契約書で、通常一律200円の印紙税(軽減措置の適用がない場合)となります。それでは具体的な税額を一覧にて確認しましょう。
| 課税文書 (印紙税法の分類) | 文書の例 | 印紙税額【令和6年現在】 |
|---|---|---|
| 第1号文書 不動産や営業権等の譲渡契約書 | 不動産売買契約書、不動産売渡証書、営業譲渡契約書 等 | 記載金額が ・1万円未満:非課税 ・1万円以上~10万円以下:200円 ・10万円超~50万円以下:400円 ・50万円超~100万円以下:1,000円 ・100万円超~500万円以下:2,000円 ・500万円超~1,000万円以下:10,000円 ・1,000万円超~5,000万円以下:20,000円 ・5,000万円超~1億円以下:60,000円 ・1億円超~5億円以下:100,000円 ・5億円超~10億円以下:200,000円 ・10億円超~50億円以下:400,000円 ・50億円超:600,000円 ※契約金額の記載がない場合:200円 ※不動産譲渡契約書については平成26年から令和9年(2027年)3月まで軽減措置あり |
| 第2号文書 請負に関する契約書 | 建設工事請負契約書、映画出演契約書、物品の製造請負契約書 等 | 記載金額が ・1万円未満:非課税 ・1万円以上~100万円以下:200円 ・100万円超~200万円以下:400円 ・200万円超~300万円以下:1,000円 ・300万円超~500万円以下:2,000円 ・500万円超~1,000万円以下:10,000円 ・1,000万円超~5,000万円以下:20,000円 ・5,000万円超~1億円以下:60,000円 ・1億円超~5億円以下:100,000円 ・5億円超~10億円以下:200,000円 ・10億円超~50億円以下:400,000円 ・50億円超:600,000円 ※契約金額の記載がない場合:200円 ※建設工事請負契約書について平成26年~令和9年3月は高額の場合に軽減措置あり |
| 第3号文書 約束手形・為替手形 | 手形(為替手形・約束手形) ※手形の複本・謄本は非課税 | 手形金額が ・10万円未満:非課税 ・10万円以上~100万円以下:200円 ・100万円超~200万円以下:400円 ・200万円超~300万円以下:600円 ・300万円超~500万円以下:1,000円 ・500万円超~1,000万円以下:2,000円 ・1,000万円超~2,000万円以下:4,000円 ・2,000万円超~3,000万円以下:6,000円 ・3,000万円超~5,000万円以下:10,000円 ・5,000万円超~1億円以下:20,000円 ・1億円超~2億円以下:40,000円 ・2億円超~3億円以下:60,000円 ・3億円超~5億円以下:100,000円 ・5億円超~10億円以下:150,000円 ・10億円超:200,000円 ※一部の手形(一覧払手形・銀行間の手形等)は一律200円 |
| 第4号文書 株券・社債券・出資証券 等 | 株券、社債券、投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券 等 | 券面金額が ・500万円以下:200円 ・500万円超~1,000万円以下:1,000円 ・1,000万円超~5,000万円以下:2,000円 ・5,000万円超~1億円以下:10,000円 ・1億円超:20,000円 ※非課税:日銀や特定法人発行の出資証券等 |
| 第5号文書 合併契約書・分割契約書 等 | 会社の合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書 (会社法や保険業法に基づくもの) | 一律 40,000円 |
| 第6号文書 定款(株式会社等の設立時) | 株式会社・合同会社などの設立時に作成する定款の原本 | 一律 40,000円 ※非課税:株式会社・相互会社の電磁的定款など |
| 第7号文書 継続的取引の基本契約書 | 例:基本売買取引契約書、代理店契約書、業務委託契約書 等 | 一律 4,000円 ※契約期間3ヶ月以内かつ更新なしの場合は除く |
| 第8号文書 預金証書・貯金証書 | 銀行の預金証書、ゆうちょ銀行の貯金証書 等 | 一律 200円 ※非課税:信用金庫等が発行する1万円未満のもの |
| 第9号文書 倉荷証券・船荷証券 等 | 倉庫証券、船荷証券(B/L)、複合運送証券 等 | 一律 200円 |
| 第10号文書 保険証券 | 火災保険や生命保険など各種保険の保険証券 | 一律 200円 |
| 第11号文書 信用状 | 銀行等が発行する信用状(Letter of Credit) | 一律 200円 |
| 第12号文書 信託に関する契約書 | 信託契約書、信託証書 等 | 一律 200円 |
| 第13号文書 債務の保証契約書 | 保証契約書(※主たる債務の契約書に併記の場合は除く) | 一律 200円 ※非課税:身元保証に関する契約書(身元保証法による) |
| 第14号文書 金銭または有価証券の寄託に関する契約書 | 金銭消費寄託契約書、有価証券の預り証 など | 一律 200円 |
| 第15号文書 債権譲渡・債務引受け契約書 | 債権譲渡契約書、債務引受契約書 | 記載金額が ・1万円未満:非課税 ・1万円以上:200円 ※金額未記載の場合も200円 |
| 第16号文書 配当金領収書・配当金通知 | 株式や出資の配当金の領収証、配当金振込通知書 | 記載の配当金額が ・3千円未満:非課税 ・3千円以上:200円 ※金額未記載の場合も200円 |
| 第17号文書 金銭または有価証券の受取書 (領収証等) | 領収証、レシート、代金受取書 ※いわゆる領収書類で、「営業に関しないもの」は非課税 | (A) 売上代金に係る受取書の場合 ・5万円未満:非課税 ・5万円以上~100万円以下:200円 ・100万円超~200万円以下:400円 ・200万円超~300万円以下:600円 ・300万円超~500万円以下:1,000円 ・500万円超~1,000万円以下:2,000円 ・1,000万円超~2,000万円以下:4,000円 ・2,000万円超~3,000万円以下:6,000円 ・3,000万円超~5,000万円以下:10,000円 ・5,000万円超~1億円以下:20,000円 ・1億円超~2億円以下:40,000円 ・2億円超~3億円以下:60,000円 ・3億円超~5億円以下:100,000円 ・5億円超~10億円以下:150,000円 ・10億円超:200,000円 ※金額未記載の場合:200円 (B) 売上代金以外の受取書の場合 ・5万円未満:非課税 ・5万円以上:200円 ※金額未記載の場合:200円 |
| 第18号文書 通帳(預金・信託通帳等) | 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 | 1年ごとに200円 ※非課税:納税準備預金通帳や、信用金庫等の通帳など |
| 第19号文書 その他の通帳 | 融資(消費貸借)通帳、請負通帳、有価証券預り通帳 等 | 1年ごとに400円 ※第18号文書に該当する通帳を除く |
| 第20号文書 判取帳(はんとりちょう) | ※金銭の出納を綴った帳簿の一種(現在はあまり一般的でない) | 1年ごとに4,000円 |
上記のように、印紙税額は文書の種類ごとに200円から最大60万円まで幅があります。
例えば日常的な金銭のやり取りでは領収証がよく利用されますが、「5万円未満の領収書なら印紙税が非課税で、5万円以上なら200円の印紙を貼る」というルールは多くの方が聞いたことがあるでしょう。これは2014年の改正によって非課税枠が拡大され、領収書は5万円未満なら印紙不要になったためです。逆に言えば、5万円以上の領収書には額に応じた印紙税が課税される仕組みです。
このように売上代金に関する受取書(領収証)は額面に応じて段階課税されますが、それ以外の受取書(例:借入金の受取書など)は一律200円(5万円未満なら非課税)です。また、実際に印紙税を納める際には所定額の収入印紙を購入し文書に貼付しますが、収入印紙を貼り忘れてしまうと本来の税額の3倍もの過怠税(ペナルティ)が科されるので注意が必要です。逆に「うっかり印紙を貼りすぎた」「貼らなくてよい文書に貼ってしまった」という場合には、税務署で過誤納の手続きをすれば還付を受けることもできます。
現在、収入印紙の券種は200円から最高10万円まで各種が発行されています。
例えば左の画像は最も身近な「200円」の収入印紙です。コンビニや郵便局でも購入でき、小さな緑色の切手のような姿をしています。契約書や領収証にこの印紙を貼り、割印(消印)することで納税完了となります。収入印紙のデザインは時代により変遷していますが、現行の印紙は菊の御紋と桜の花びらがあしらわれた落ち着いた意匠です。身近な200円印紙のほかにも、1万円や5万円、10万円といった高額の印紙も存在しますので、何億円もの契約書を作成する際には複数枚ではなく高額面の印紙を貼ることで納税することになります。
印紙税額改定の歴史(明治~令和)
印紙税の歴史は非常に古く、日本では明治6年(1873年)に初めて導入されました。明治期の地租改正(地税の改革)の一環として、安定財源確保のため諸外国にならって印紙税制度が採用されたのです。当初は「受取諸証文印紙貼用心得方規則」(明治6年太政官布告第56号)という布告が定められ、領収証などの文書に印紙を貼るという仕組みが始まりました。導入当初は取引額が10円未満のごく小さな領収証などには紙そのものにあらかじめ課税模様が刷り込まれた「界紙(かいし)」という特別な用紙を使い、それ以上の額面には印紙を貼る方式だったそうです。しかし界紙は製造・運搬のコストがかかるため、**1884年(明治17年)**の改正で界紙は廃止され、すべて収入印紙を貼る方式に統一されました。今でいう「切手を貼る感覚」で税金を納めるやり方が、この頃に確立したわけですね。
その後、明治32年(1899年)には旧印紙税法(明治32年法律第54号)が制定され、印紙税制度が法律として整備されました。これが戦前・戦後を通じて約70年近く運用されます。印紙税は第二次世界大戦後の混乱期にも国の財政を支える収入源の一つでした。当時はインフレ等もあり印紙の額面や種類も変動しましたが、大枠の仕組みは維持されます。そして高度経済成長を経た昭和42年(1967年)に印紙税法が全面改正され、現在の印紙税法(昭和42年法律第23号)が施行されました。この1967年の改正で課税文書の区分が20種類(第1号~第20号)に整理され、それぞれに具体的な税率(定額または階級定額)が定められました。印紙税額一覧表の原型ができあがったのが、この時期と言えます。
印紙税額の具体的な改定も、時代に応じて行われてきました。特に昭和後期から平成にかけて事業者の負担軽減や税制簡素化の観点でいくつかの重要な改定があります。以下、主な改定の歴史を時系列でまとめます。
- 1974年(昭和49年): 領収証(第17号文書)に免税点が導入されました。従来、領収証は記載金額が1万円未満なら非課税、1万円以上は一律100円の印紙税でした。しかし中小企業の負担軽減のため、この年の改正で領収証の課税が段階税率(階級定額)に変更され、あわせて非課税とする範囲(免税点)が「1万円未満」から「3万円未満」に大幅拡大されました。この改正により当時発行される領収証の約9割が非課税となったといいます。
- 1981年(昭和56年): 印紙税法の一部改正で印紙税額の最低額が100円から200円に引き上げられました。それまで領収証などに貼付する最小の収入印紙は100円券でしたが、この改正以降は200円が最小となり、結果的に多くの課税文書で必要な印紙額が倍増しました。例えば3万円以上の領収証に貼る印紙も100円から200円に引き上げられています。これは高度成長期後のインフレ等に対応した調整でした。
- 1989年(平成元年): 消費税導入に伴う税制改革で印紙税も見直しが行われ、課税対象となる文書の範囲が縮小されました。具体的には、「土地建物の賃貸借契約書」や「物品売買(動産譲渡)の契約書」など、一部の契約書類が印紙税の非課税文書に変更されています。これらはそれ以前は印紙税が課されていましたが、消費税による課税と二重になる部分でもあり、取引実務の簡素化のため印紙税を免除する方向となりました。この改正以降、現在に至るまで賃貸借契約書や商品売買契約書には印紙税がかからないのが原則です。
- 1997年(平成9年): バブル崩壊後の景気対策の一環として、不動産売買契約書および建設工事請負契約書の印紙税軽減措置が租税特別措置法により導入されました。契約金額が一定額を超える高額な不動産・建設工事の契約について、本来の印紙税額よりも税率を低く抑える特例措置です。この措置は当初時限立法でしたが、その後景気動向を踏まえて何度も延長されています。例えば契約金額1億円の不動産売買契約書は本則では印紙税10万円のところ、軽減措置では6万円とされる、といった具合です。直近では令和9年(2027年)3月31日までこの軽減措置が延長適用されることが決まっており、大型の不動産取引などでは引き続き軽減後の印紙税額が適用されています。
- 2014年(平成26年): この年の税制改正で領収証等の非課税範囲がさらに拡大され、「5万円未満の領収書は印紙税非課税」となりました。それまで領収証の免税点は3万円未満でしたが、一挙に5万円未満まで引き上げられた形です。「5万円以上の領収書に200円の印紙を貼る」という現在のルールはこの改正によるものです。この改定は小売業や飲食業など現金取引の多い業界にとって事務負担の軽減につながり、「5万円未満なら印紙不要」という基準が広く定着しました。
以上が、明治時代から令和にかけての主な印紙税額の改定履歴と金額の推移です。印紙税収入は年間1兆円規模にも及び、現在も酒税やたばこ税に匹敵する国の財源となっています。しかし昨今は電子契約の普及により、紙の契約書を作成しなければ印紙税は不要というケースも増えています(電子文書は課税文書に該当しないため)。例えばオンラインで締結する電子契約書やメールによる請求書には印紙税はかかりません。このような時代の変化もあり、将来的に印紙税制度の在り方が見直される可能性も議論されています。とはいえ、2025年現在も紙の契約書や領収書は日々やり取りされています。印紙税額一覧表を参考にしつつ、法律で定められた適切な収入印紙を貼って、大切な文書を作成するようにしましょう。税金は正しく納めてこそ、後々のトラブルも防げるというものです。印紙を貼る際は「この文書にはいくらの印紙税が必要かな?」と、本記事の一覧表をぜひ思い出してくださいね。
参考資料(出典)
国税庁「印紙税額一覧表(令和6年11月現在)」、国税庁タックスアンサー No.7140・7141、参議院提出資料「印紙税に関する質問主意書 答弁書」、経営ハッカー『印紙の歴史から見た総まとめ』、国税庁『印紙税の手引(令和6年版)』、租税特別措置法 他。